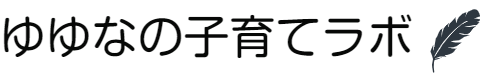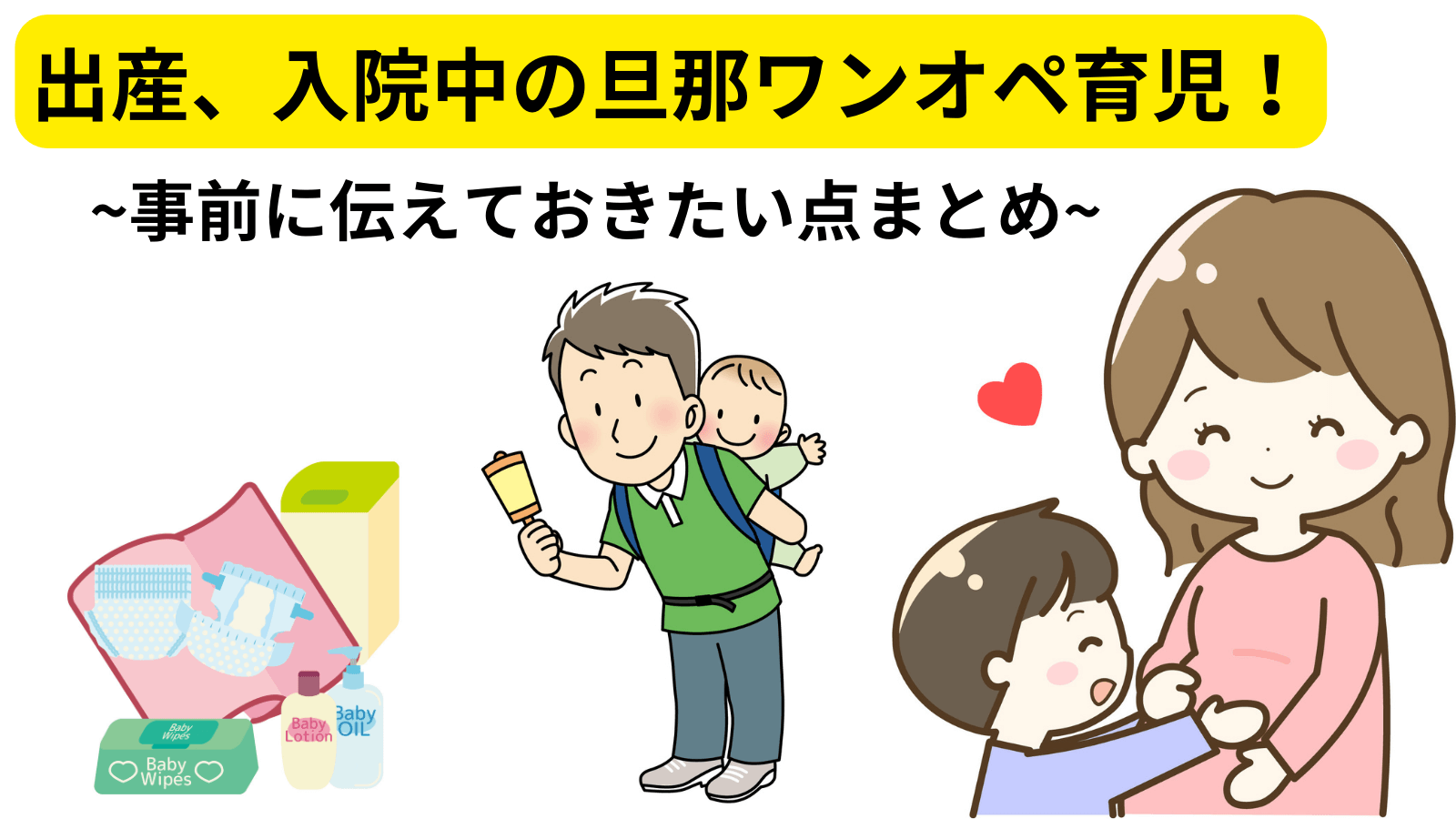こんにちは!ゆゆなです。
我が家は娘が1歳を迎える前に第2子の妊娠が発覚し、
年子で子供を授かる形となりました。
不安はありましたが里帰りはせず、
出産、入院中の娘のお世話は
旦那が担当する形で準備を進めました。
旦那に数日育児を任せるにあたり、
やっておいてよかったこと、
やっておけばよかったことについて
まとめておりますので、同じ境遇の方は
ぜひ参考にしてください。
やっておいてよかったこと
さっそく本題となりますが、
旦那に育児を任せるにあたり、平日ワンオペの私が感じる
やっておいてよかった点を紹介します。
尚、普段の旦那さんの育児参加具合に
依存致しますのでその点はご承知おきください。
基本的な育児
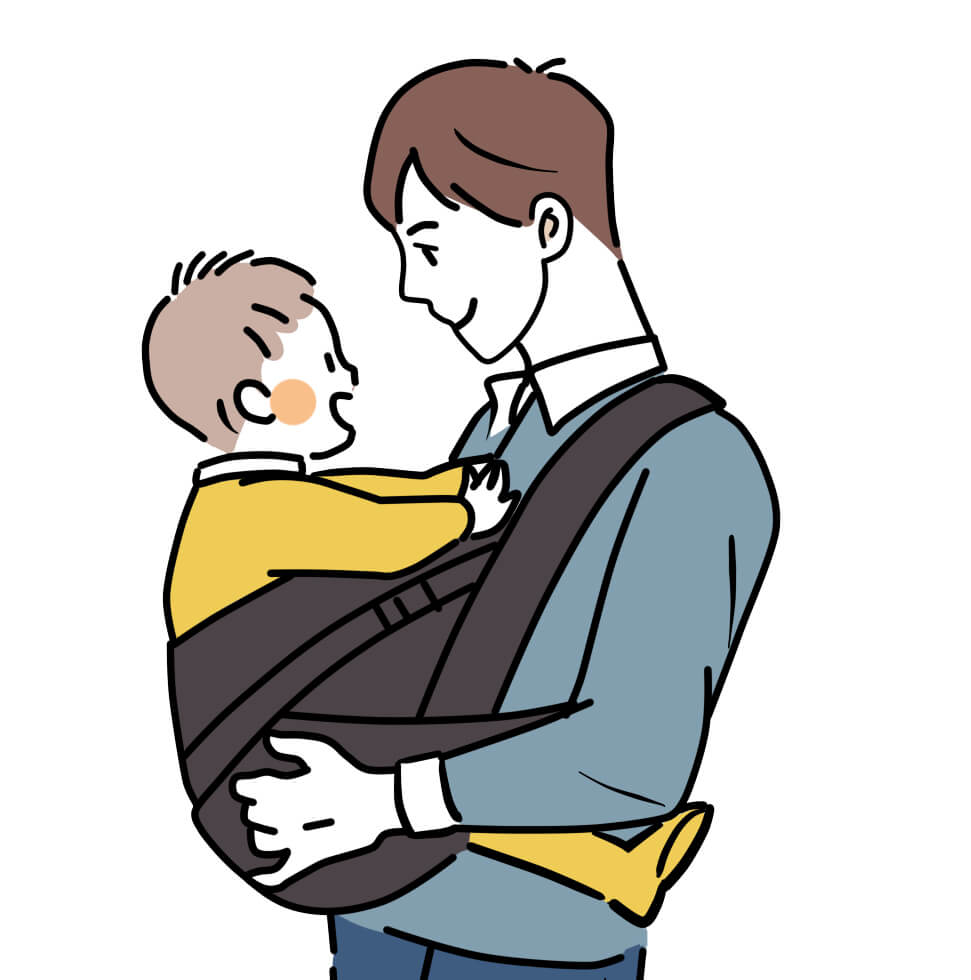
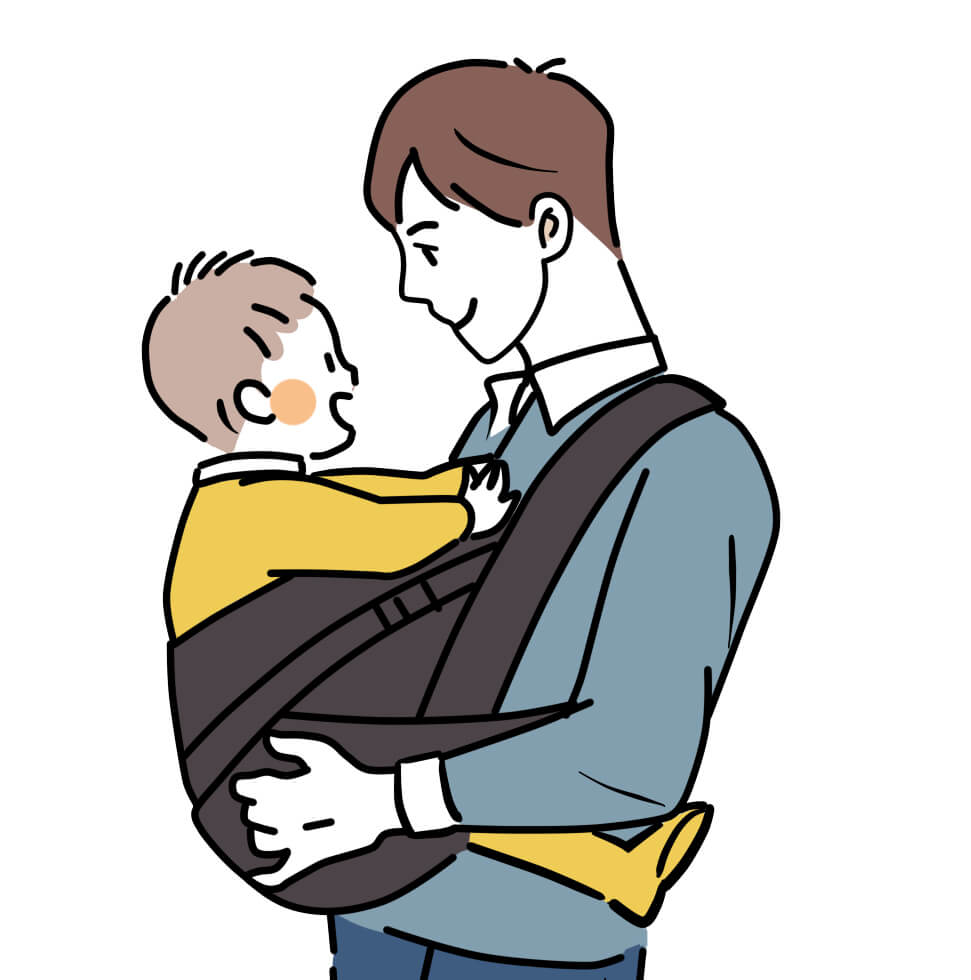
おむつ替えや離乳食、お風呂、歯ブラシ、
寝かしつけといった基本的な育児は
マスターする必要があります。
尚、育児についてレクチャーする際は、
・1日の飲料量は〇ml目安
・おむつの交換回数は約〇回
・爪は〇mm伸びたら切る
・睡眠時間は約〇時間
・1回に食べさせる離乳食は〇g
など、できるだけ定量的な情報を伝えることで、
確実な育児習得につながり、入院中の安心感につながります。
我が家は長女の誕生時に旦那が2か月ほど
育休を取得していたため、特に教えることは無かったのですが、
0からのスタートとなる場合、スムーズにできるまでは
ある程度時間を要するため余裕を持った計画を立てることをおすすめします。
夫婦で育児記録アプリの導入
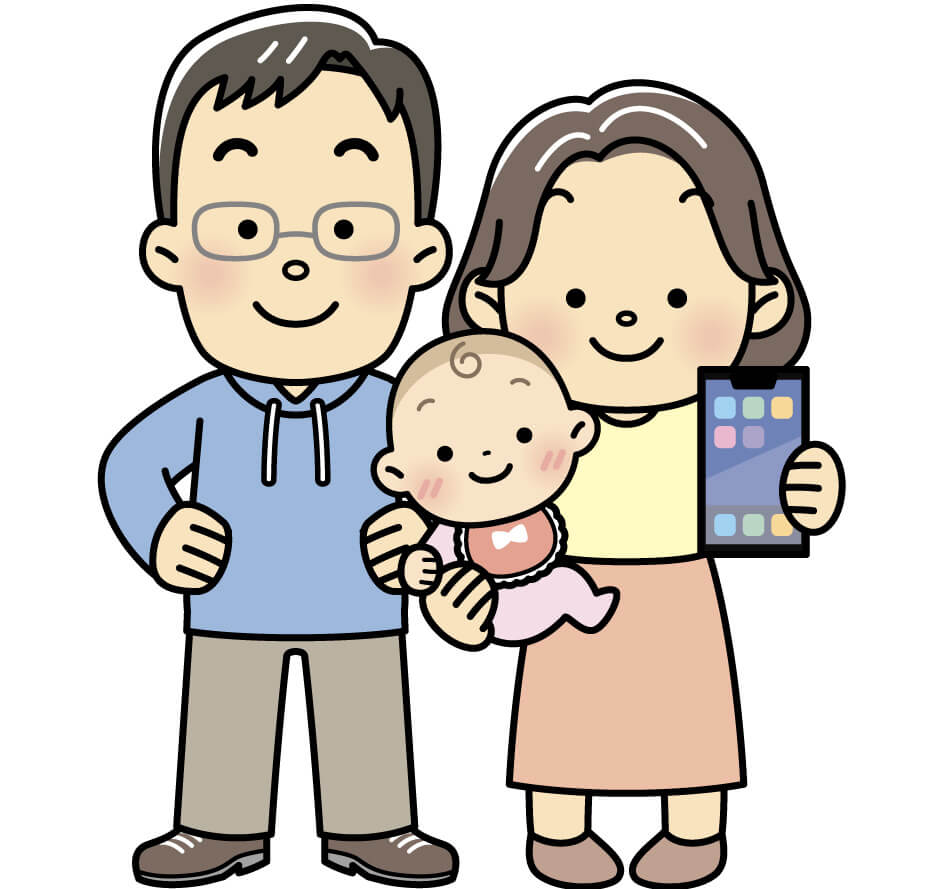
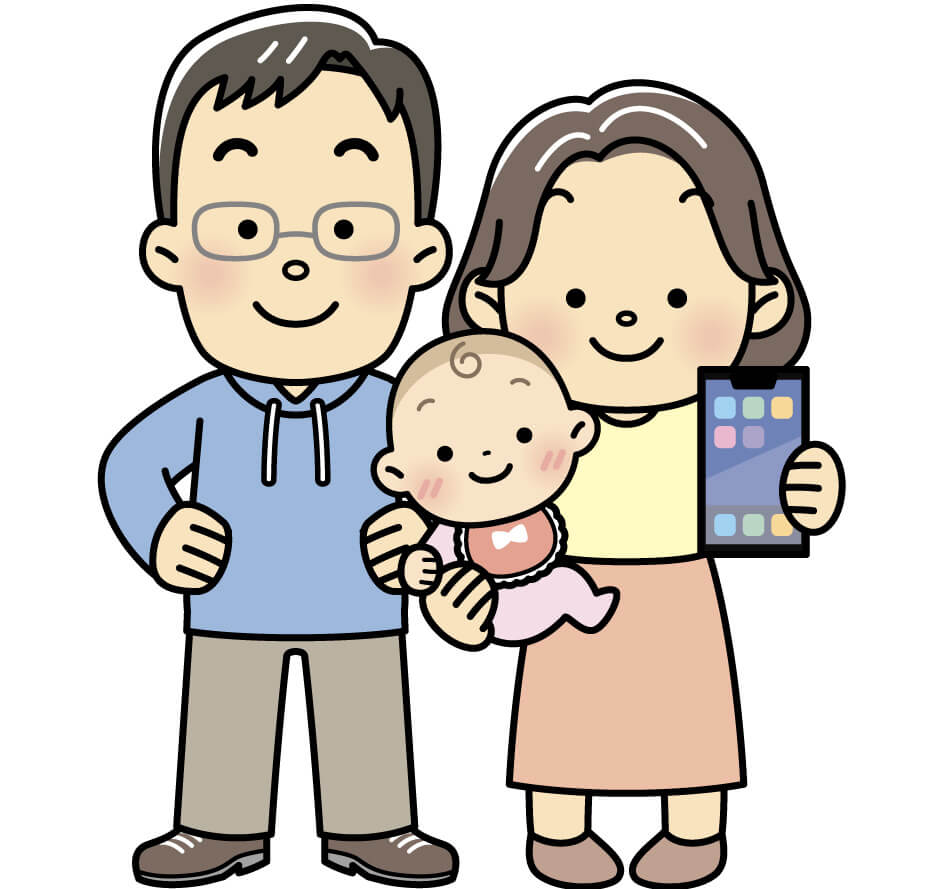
私のスマホにしか育児アプリを
インストールしていなかったため、
旦那のスマホにもインストールしました。
夫婦で同じ育児記録アプリを導入することで、
データの共有が可能になるため、産後の入院中もデータから
ある程度状況を把握でき、気になる点があれば指摘できます。
我が家は「たまひよ」を使っているのですが、
無料でここまでの機能があれば不満は無いです。
まだ育児記録アプリを使用されていない方はぜひ一度使ってみてください。
最近の傾向や日常生活での注意点の共有
最近お気に入りのおもちゃや、どこで転びやすいのか、
どのようなイタズラをしがちなのかを
共有しておきましょう。
子供の成長は思っている以上に速いため、
普段育児をしていない旦那さんの想定と現実は大きく
異なっていることが多いです。
行きつけの病院の共有


出産時の病院のみを使っている場合、
旦那さんも把握していると思いますので、
特別意識する必要は無いです。
しかし、病院を変えている場合や、
土日祝は別の病院に行っているケースでは
診察券の受け渡しと合わせて病院の場所や
雰囲気を共有しておきましょう。
離乳食のストック、飲み物のストック


出産のタイミングと同じくして
旦那さんのワンオペ育児が始まります。
旦那さん次第ですが、突然始まるワンオペ育児で
離乳食を作る余裕がないケースが多いかと思いますので、
離乳食や飲み物のストックはあると非常に安心できます。
やっておけばよかったこと
ママが普段無意識に行っていることは意外と多く、
ママの常識が旦那さんの常識であるとは限りません。
このため、旦那さんへ伝えなければならない
情報が比較的多くなってしまい、伝達漏れが生じます。
我が家でも「あれをやっておけばよかった」、
「あれを伝え忘れた」といった点がいくつかありましたので、
紹介させて頂きます。
NG事項の共有
やるべきことの共有を優先してしまい
はちみつ等の食べさせてはダメなものや、使ってはいけないもの、
やってはいけないことの共有が漏れてしまいました。
普段ママが何気なく気を付けている点をどこまで共有できるかが
重要ですのでぜひ時間のある際に洗い出してみてください。
背部叩打法等のレクチャー
幸いにも我が家は私が退院するまで、
特別トラブルが無かったのですが、
普段育児をしない旦那さんはトラブル時の対処を
知らないケースが多いかと思います。
背部叩打法や、トラブル時は動画撮影をする等、
最低限の知識は共有しておくようにしましょう。
ベビーフードの用意
私の場合、離乳食のストック作りに意識が向きすぎてしまったのですが、
温めるだけで味付けのされたバランスの良い
離乳食を与えられるので、準備すべきだったと感じます。
離乳食のストックを用意していたとしても
いざ食べさせる際の味付けや栄養バランスを考慮して
何を食べさせるか考える必要があるため、
高確率で旦那さんから相談が来ます。
細かいこだわりの共有
育児にこだわりがある点はなるべく共有するようにしましょう。
我が家の場合、洗濯した子供服の収納場所、たたみ方が
私と違っていたため、退院後に思わずため息が出てしまいました。
退院後は新しく誕生したベビーのお世話にかかりきりになるため、
退院後に余計な体力を使わないように工夫していきましょう。
まとめ


旦那さんに数日育児を任せる際に
意識しておきたいポイントを紹介させて頂きました。
最近は男性の育休を推進する企業も増えてきており、
育児に積極的な旦那さんも多くなってきていると
思いますが、旦那さんに完全に育児を任せられる方は
あまり多くないかと思います。
私のように出産時など、旦那さんに育児をしてもらうしか
無い状況も起こりうるため、その際に本記事が
少しでも参考になれば幸いです。